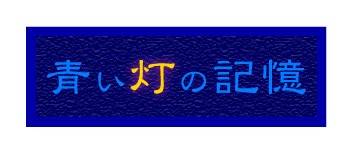

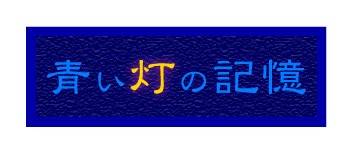 |
 |
僕の記憶のずっと奥の方に、青い灯の記憶がある。 そんな光景のひとつとして。 あれはまだ僕が小学校の一年生の頃。 さらにもうひとつ。 そうしたものが、幾つかある。
|
|
データですが、作曲者はクロード・モルガンで、日本語の作詞家は加藤直。原曲はHasta Luegoといって、フランス人歌手ユーグ・オーフレイが歌ってヨーロッパでヒットしたそうです。放送は、1977年2月と3月。ちなみに、「アスタ・ルエゴ」とは、スペイン語で、「さようなら」とか、「また会いましょう」とか言う意味だとか。日本語の歌詞では、そのままの形で出てきています。現在、つい最近のことですが、CDでも入手できるようになったのですが、それは一城みゆ希さんが歌いなおしたものです。オリジナルは研ナオコ。印象はかなり違います。昔キングレコードから出ていたLPにはそのままの形でで収録されているようですが、入手はかなり困難だと思います。また、ネットで分かった事は、この曲が再放送されなくなったのは、研ナオコが薬物で捕まったせいだとか。うわあ、もう時効でしょ、NHKさん。お願いですから、再放送してくださいな。勿体なすぎます。 8/25/2003
|
|
子供の頃から、灯台という言葉は、僕にとってどこか特別なものであり続けているように思う。 それから一、二年して、僕は実際に父に潮岬の灯台につれていってもらった。連れて行ってくれと頼んだわけではなく、なぜか連れてゆかれたのだ。 僕は物心がついてから、ほとんど父と過ごした記憶がない。父は家に寄り付かず、小学校の三年生からは祖母の家に預けられて、その冬には神戸に移り、母と祖母に育てられた。別に父を恨むつもりも無く、父がもう鬼籍に入っている今となっては、もう母と祖母に感謝するだけで、どうでもよいことだ。ただ、灯台のことを思うと、初めに浮かぶのは父のことだ。あの歌の事と、潮岬の灯台の上から見た光景のことだ。 妻とは幾つかの灯台を廻った。 8/28/2003 |
|
9/6.2003 |
|
11/17 2003 |
|
小学校二年生、八歳の夏の夜ことだ。 大阪の家はもともと呉服屋で、とはいうものの田舎の店だから、表向きにはひなびた洋品店にしか見えない。たまにする展示会などで、そうか呉服屋だったのだと分かる程度の店だ。店は祖父がやっていたのだが、呉服を扱っているよりは、田んぼや畑やミカン山での作業のほうが多かった。小学校に上がる前から、僕は店番をやったり、田畑での収穫を、ほとんどままごと程度だろうが、手伝っていた。そして、それが面白かった。 2004.1.19
|
|
長い間、謎の映画があった。 しかし、話が進むにつれ、僕は次第にその映画に見入っていった。 この映画が、僕には長い間忘れ難かった。だが、つい最近まで僕はこの映画のタイトルを「僕は6歳だと思っていた。だからどうしても探せず、この映画は僕にとって謎の映画だった。しかし、最近ようやくこの映画のタイトルは「ボクは5才」だと知った。微妙に、けれど結構、致命的に間違っていたようだ。残念ながら、今そう簡単に見れるという映画ではないが(一度だけビデオがレンタル用に出たことがあるようだし、スカパーで放送されたこともあるらしい)、DVD化の話もあったらしいし(流れてしまったようだけれど)、いずれ見ることができるかもしれない。 2004.7.16 |
|