|
はじめに
ホジスンの生涯
主要単行本リスト
ホジスン関連年表

―沈黙の家から―
・四大長編の執筆時期について
・夏目漱石は『異次元を覗く家』を読んだことがあるのか?
・ホジスン対フーディニ
・ホジスン作品の古書価のはなし
・ラヴクラフトのホジスン評
・マタンゴのはなし

―試訳―
・The Goddessof Death
(死の女神)
・Eloi Eloi Lama Sabachthani
(エリ・エリ・レマ・
サバクタニ)
・Through the Vortex of A Cyclone
(サイクロンの渦を抜けて)
・Date 1965: Modern Warfare
(1965年:現代の戦争)
・The Riven Night
(裂かれた夜)
・The Haunted Pampero
(ホーンテッド・”パンペロ”)
・The Room of Fear
(恐怖の部屋)
・Out of the Storm
(嵐より)

リンク

Sigsand
manuscript

漂着の浜辺から

Seaside
Junk Foods |
ストーリー
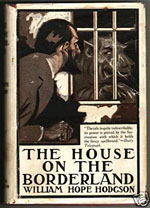 この本は二重構造になっていて、偶然発見した不思議な手記をホジスンが僅かに注釈を加えつつ、ほぼそのままの形で紹介するという形式を取っている。つまりこの本では、ホジスンは架空の本の紹介者という立場を取っている訳だ。 この本は二重構造になっていて、偶然発見した不思議な手記をホジスンが僅かに注釈を加えつつ、ほぼそのままの形で紹介するという形式を取っている。つまりこの本では、ホジスンは架空の本の紹介者という立場を取っている訳だ。
物語は、ホジスンが友人とアイルランドの西外れにあるクライトンという小さな村に休暇で訪れる所から始まる。その村の外れで、二人は奇妙な形をした巨大な廃墟を発見し、興味本位で探検しているうちに、土に半ば埋もれた一冊の本を発見する。その本は、かつてこの廃墟に妹と一匹の犬とともに暮らしていた一人の老人が書き残した手記で、この廃墟に起きた恐るべきできごとについて記されていた。
夜毎襲い来る、豚に似た獣人の群れとの戦い。不思議な光とともに老人に起こった幻視。その幻視の中で、時間加速現象が連れてゆく、宇宙の終末の光景。やがて彼らに訪れた破滅の時の、その寸前まで、手記は信じがたい物語を綴ってゆく。
解説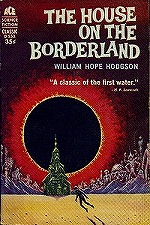
この作品が、ホジスンの全長編中で最もまとまりがよく、かつ印象的だというのが一般的な評価で、代表作として上げられる事が多い。この作品に影響を受けたと公言している作家も多くいるし、出版された回数が最も多いことも事実だ。長く忘れられていたホジスンの、再評価のきっかけになったのもこの本である。漫画やカセットブックにもなっている。
この本が代表作であることには異論はないが、公平に見て、この作品は明らかにウェルズの名作「タイムマシン」の強い影響下にある(タイムマシンの初版は
1895年。異次元を覗く家は1908年。ホジスンが「タイムマシン」を持っていたという証言もある)。あるいは、当時流行していたという、フラマリオンら科学者たちによる終末思想の影響下にある。だから、この作品で最大の見せ場である、時間が加速してゆき、霊魂のみの存在となった主人公が世界の終わりをかいま見るというシーンの、アイデアそのものに対する評価は、残念ながら割り引いて考える必要があるだろう。ちなみに、日本では、かつてその部分だけを短編として訳出された事がある。
とはいえ、その事がホジスンと、そしてこの作品の価値を低めるものではない。ここでわざわざウェルズの名前を出したのは、そういうことを言いたいわけではなくて、ただホジスンの特性をはっきりとしておきたかったからだ。
時間を超えて終末の光景を覗くというアイデアそのものは、確かにウェルズらの影響下にあるのだろうし、地球を宇宙的な視点から見るというのはフラマリオンらの影響が強いのだろう。だが、そこで描き出されているイマジネーションは明らかにホジスンならではのもので、鮮烈さという点では比較にならないように思う。ではその鮮烈さは、どこから来ているのだろう。
これは、一つにはホジスンの光と色彩に対する鮮烈な感性が生み出しているのだと思う。
こちらの感覚が飲み込まれて行くような気持ちになるホジスンのイメージ喚起力は、まるで薬物の生み出す幻覚のようで、殆ど魔術的といっていい。そしてそれは、他の作家には殆どみられないほどの豊かな色彩に彩られている。しかもその色彩は、僕は思うのだが、顔料や染料のそれではなく、光そのものの色彩、それもとても濃厚な色彩のような気がする。ホジスンの筆は、物語のストーリーだけではなく、その影と光、そして色彩をしっかりと捕らえて行く。
ホジスンが数多い幻想小説作家のなかでも「特別」であるのは、まさにこの点ではないか。ホジスンは何か奇妙なものを書く時には、必ず闇の中にはっとするような色彩を描き出す。それが、他に類を見ない濃密な印象を生み出すのだ。
それは、この作品でも同じである。「緑の太陽」などという奇妙なものはウェルズには生み出せなかったし、「蒼く穏やかな光に照らされた《沈黙の海
》」などという不思議なイメージも同様だ。どちらも強い光を作品の中で放っていて、読者の目を眩ませるほどだ。しかも、強い光を放つのはそれだけではないのである。ホジスンの「描き出す」もののひとつひとつが、そうした鮮やかな色彩を持っている。
長く自然を相手に生きてきたホジスンにとって、周りをとりまく自然や、空の移り変わりの鮮やかさを畏怖する気持ちは、同時代の都会の作家とは比べてもとりわけ強かったはずだ。ホジスンの作品が感覚的なのは、生来の気質に加えて、そうした環境によって研ぎ澄まされた結果なのだろう。
いささか話が横道にそれてしまっていたかもしれない。
「異次元を覗く家」を、内容に沿ってもう少し深く考えようと思う。
「異次元を覗く家」は、言うまでもなく不思議な話であるが、読み方によって幾つかの解釈が出来る。解釈が大きく分かれるのは、一体、主人公は正常だったのか、それとも精神に異常をきたしていたのかという点だ。普通に読めば、異常な出来事が実際に起こったものとして読み進めてゆくことになるわけだが、もしそれが主人公の幻覚の生んだものだったなら、物語はまた別の意味で異様なものとなる。
大体、この物語は最初から最後まで、何一つはっきりとした説明がなされるということがない。そもそも、手記の老人の素性が全くわからない。どうして妹とふたりで暮らしているのか、どうしていわくつきの家をわざわざ選んで住もうと考えたのか、怪異が起こっているのに、どうして家を離れようとしなかったのか。なるほど、一応かつての恋人らしき女性と再び夢幻の世界で出会えることができたということなどが、説明らしく挿入されてはいるが、自分ひとりだけならともかく、妹まで巻き込む必要はなかったのではないか?それに、どうして完璧に自分たちの素性が分からないようにしていたのか。第一、後日談の中でも暗示されているように思えるのだが、手記の筆者が「わたしは老人だ」と断っているにも関わらず、これだけの立ち回りを老人ができるはずはなく、実際はそれほどの年齢ではないのではないか。短編「夜の声」でも、語り手は自分のことを最初「老人」と紹介していたが、実際の年齢はまだ若いということが後で分かるようになっていた。これも、もしかしたらそういうことなのかもしれない。ではなぜ、彼は自分を老人だと書いたのか。そして、何十年もこの家に住んでいると書いたのか。読めば読むほど、分からないことばかりが増えて行く。普通に考えれば、こうした条件下では、老人がこの家にやってきたのは何らかの明白な理由があってのことだという結論が出るのが普通だ。ところが、手記をどう辿ってもそうした理由らしきものは見つからない。では、なぜ彼らは人目を避けるようなこんな家を選んで、住もうと考えたのか。誰にも会いたくないと考えるほど世にすねた老人だったのか、それとも、語られはしないが、何か罪を背負っていた兄妹だったのか。
そうしたことは、物語の中から読み取ることは出来ない。読み手がそれぞれに考えるしかない。だが、物語の中で、怪異を実際に体験するのは兄ばかりで、妹の方は殆どその家に今起こっていることを知らないでいるようだという描写がある。実際、主人公の妹の影の薄さは驚くほどだ。それは、一体どういうことなのか。もしかしたら、怪異など殆ど実際には起こっていないという意味なのか。としたなら、この物語の中で起こっている怪異というものは、実際には兄の幻想だということになる。そう考えれば、殺戮したはずの豚の化け物の死骸のないことも簡単に説明がつく。
そう考えて、この物語を最初から読み直すと、例えばこのように読めるかもしれない。
主人公は、おそらくはかつての恋人を失った寂しさから、何か「悪しきもの」に関わっていた。それで、その研究を完成させるため、わざわざ一つの「場」であるこの「家」に移ってきた。この時点で、主人公はやや気が狂っていて、自分のしていることが半ばわからなくなっている(ここまでの部分は、ただ単に主人公が世をすねていて、半ば気が狂いかけているとだけ考えてもいい)。妹は兄に対する半ば恐怖から、ずっと付き添わされている。主人公のそうした感情が、もともと「家」の持っていた「禍禍しさ」とシンクロして、「邪悪なものたち」の進入を許すことになる。だが、その「邪悪なものたち」は、あくまでも精神的なものに進入してくる「魂を汚すもの」である。したがって、主人公の精神が幾ら病んで幻を見ようとも、健全さをまだ保っている妹には見えない。妹の影が薄いのは、異常な行動をとる主人公を恐れて、出来るだけ関わらないようにしているためだ。主人公がかつての恋人と思われる女性と逢瀬を重ねるシーンが挿入されるのは、魂を汚すことを選んだ主人公に対する「悪しきもの」の見せる「見返えり」なのかもしれないし、あるいは、『神曲』のベアトリーチェのエピソードを意識したものなのかもしれない。
手記の最後で、主人公は犬を殺し、一人で銃架を見ながら、何かがやってくる気配におびえている。そして、唐突に手記は終わる。これは、もしかしたら実際に部屋にやってきたのは妹だったのかもしれない。その後に起こったであろう悲劇は容易に想像がつく。それによって、この家の「邪悪」は完成し、この場での役目を終えて、時空の向こうへ消え去ったのだろうか。
上の例は、極端に想像力を膨らませたものだが、例えばそのように読もうと思えば読めなくもないのである。
あるいは、それほど大きく想像力を用いなくても、この物語の中に、近親相姦の影を読み取ることはできるかもしれない。家の地下に広がる奈落には、「死の影の谷」を暗示するものも読み取ることもできるだろう。つまりこの家の邪悪というものは、精神の堕落を意味するものであるというわけだ。
もしかしたら、 実際には、近親相姦は行われていないのかもしれない。それは、兄の妹に対する一方的な気持ちにすぎないのかもしれない。その感情との戦いが、怪異との戦いという形になって夜毎主人公を襲い、別の世界でのその気持ちの成就を願う気持ちが「沈黙の海」での逢瀬という形になって現れたのかもしれない。だからこそ、怪異に直面するのは常に書き手である兄だけなのだろう。つまり、怪異は実際には起こってはおらず、妹は常に狂気の行動をとる兄に内心怯えているから、常に息を潜めているというわけである。そして最後のシーンは、おそらく兄が妹を射殺したということを暗示しているのだろう。そしてその罪の重さに、彼らは家ごと奈落へと落ちてゆくのである。
「異次元を覗く家」という物語の骨格は、救罪されることなく奈落へ落ちてゆく兄妹の物語という、おそらくそのようなものだろうが、実際のところ、この物語での読みどころは「家」が時空を越えてゆくというシーンの面白さだから、そちらを楽しむのがこの小説の読み方なのかもしれない。そちらのシーンについては、また別項を設けて考えてみたい。
最後に、これは蛇足として付け足すのだが、この物語の中で重要な「家」と、ナイトランドに出てくる「沈黙の家」とは、あるいは同じ物ではないかと思う。物語が違うのだから、当然、全く同じ物というわけではない訳だが、ホジスンの中にあるイメージとしては同じ物として認識されていたのではないかと思うのだが、そう考えるのはいささか強引にすぎるだろうか?
1/書誌データ
2/ストーリーと解説
|
―長編 ―
<ボーダーランド三部作>
・ The Boats of the "Glen Carrig"
1/2/3/
・異次元を覗く家
1/2/3/
・The Ghost Pirates
1/2/3/
・ナイトランド
1/2/3/4/5/6
―連作短編集―
・幽霊狩人カーナッキ
1/2/
・Captain Gault
―短編集―
・Men of the Deep Waters
・The Luck of the Strong
・Poems and The Dream of X
・海ふかく
・Out of the Storm
・The Haunted Pampero
・Terrors of the Sea
・The Collected Fiction of William Hope
Hodgson
・The Wandering Soul
・夜の声(日本独自編集)
―詩集―
・The Calling of the Sea
・The Voice of the Ocean
・The Lost Poetry
―短編作品―
―既訳短編―
・夜の声
・失われた子供たちの谷
・陽動作戦
・石の船
・静寂の海から
・難破船
・熱帯の恐怖
・海馬
・水槽の恐怖
・海藻の中に潜むもの
・帰り船≪シャムラーケン号≫
・ランシング号の乗組員
・漂流船の謎
・グレイケン号の発見
・カビの船
・ウドの島
・岬の冒険
・暁に聞こえる呼び声
・ミドル島に棲むもの
・死の女神
・船橋にて
・ホーンテッド・”パンペロ”
・嵐より
・裂かれた夜
・わたしの家は、
祈り人の家と呼ばれるべきである
1965年:現代の戦争
―未訳短編―
・The Albatross
・A Timely Escape
・The Heathern's Revenge
・The Captain of the Onion Boat
・Bullion
・The Phantom Ship
***
・R.M.S Empress of Australia
|